申請書
-

こんにちは田邉です。
今回は、2025年度に新設の「新事業進出補助金」についてご紹介します。① はじめに:第2回公募の見通し
2025年7月15日に締め切られた第1回公募は、電子申請システムの稼働開始が6月17日と準備期間が短く、7月に入ってからは申請が集中したことで、サーバーの一時的にダウンや、ログインが不安定になるといったトラブルが発生しました。本来の締切日は7月10日でしたが、これらを受けて5日間の延長措置が取られました。採択結果は10月に発表される見込みで、第2回公募は10月中旬ごろの開始が想定されています。
本補助金は、計画書様式や添付資料など提出物が多岐にわたり、会社全体の協力体制を整えるまでに時間を要します。これが第1回で浮き彫りになった最大の教訓です。② 補助金の位置づけと活用対象
本補助金は「既存事業と異なる市場への進出」を後押しする制度です。類似制度として事業再構築補助金がありますが、再構築補助金が「業種や事業モデルそのものを大きく変える取り組み」を対象とするのに対し、新事業進出補助金は、「既存の強みを活かしながら、新たな市場・顧客に展開する事業」に絞って支援しています。
新事業の定義既存事業と比較して、①市場 ②顧客層 ③提供価値のいずれもが明確に異なること。
形容詞を付け替えただけの「高性能版」「新型モデル」では要件を満たしません。
補助対象経費は、設備費・専用ソフトウェア・外注加工費・建物費などが中心です。リース契約による取得は原則として補助対象外ですが、リース会社との共同申請を行うことで対象となる場合があります。購入または割賦による取得を前提とした資金計画が一般的です。③申請前に最低限整理しておきたいこと
●新事業として成立するかの仮ストーリーを描く
市場が変わっているか?既存顧客と異なるか?という視点で“ひとまず説明できる状態”にすることが第一歩です。
●導入設備と売上計画のつながりを明文化
この設備を入れることで、どの製品が、どの顧客向けに、どれだけ売れるのか
その関係性を説明できるように準備しておきましょう。●GビズIDの前準備を忘れずに
法人代表者アカウントの取得には1週間以上かかるケースもあり、 申請直前に慌てる原因となります。
また、ID管理の混乱も少なくなく、「誰が申請操作を行うのか」「申請権限は適切か」といった点を早めに整理しておくことが重要です。④申請書作成でつまずきやすい注意点
●賃上げ要件の適用範囲対象
従業員の選定ミスがあると交付後に減額・返還リスクが生じます。(役員を除く雇用契約がある従業員が対象)
●スケジュールの現実性
交付決定前の発注・工事着手はすべて“対象外経費”となります。資材調達リードタイムや建屋改修工期を保守的に見積もることが肝要です。
●資金調達計画の整合
補助金だけでは全ての費用をまかなえないため、自己負担分や補助対象外の費用も含めた資金を用意する必要があります。そのうえで、設備代金や工事費の支払いタイミングと、自己資金・借入金が実際に使える時期がずれていないか、事前にしっかり確認しておきましょう。
⑤おわりに:今こそ準備を
本補助金は今年度に新設された制度であり、申請対応も初めてのケースが多くなっています。補助金額が大きいため、申請には2~3か月以上の準備期間を設けることが理想的です。外部専門家や金融機関のアドバイスを受けながら、審査項目を十分に押さえた計画書を作成するためには、入念な事前準備が採択の鍵となります。
補助金の申請を検討されている方は、早めの準備を進めることをお勧めします。当社では無料相談に対応しておりますので、賃上げや特例措置の条件等、ご質問はお気軽にご相談ください。
-
こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の日野です。
補助金申請で準備する資料の中で、最も注力する必要があるのは事業計画書かと思います。公募要領にも計画書に記載する内容について言及されていますが、なかなか公募要領を読んでもイメージしづらいという方もいらっしゃるかと思います。
そのような方は、会社の採用試験などの面接をイメージして頂けると理解しやすいと思います。
面接では、「(1)自己紹介」、「(2)自分の長所、短所」、「(3)志望動機」「(4)今後のキャリアプラン」という流れで面接官にアピールするかと思いますが、計画書でも大まかな流れはほとんど同じです。
以下で、面接の流れに併せて、事業計画書の内容について説明いたします。(1)自己紹介⇒会社紹介
自社で行っている事業内容、経営ミッション、企業理念について紹介します。
(2)自分の長所、短所⇒自社の強み、弱み
自社が誇れる部分(強み)、苦手としている部分(弱み)を説明します。
(3)志望動機⇒①事業を行う理由、②補助金を活用し設備投資をする理由
なぜその事業を行うのか、なぜ補助金を活用するのかを説明します。この項目が一番重要な部分となります。
具体的には、以下の内容となります。
① その事業を行う理由
・市場規模は十分あるのか
・顧客からのニーズはあるのか
・自社の強みを活かして、他社と差別化できるか
② 補助金を活用し設備投資する理由
・事業を行うにあたって何が問題になっているか
・設備投資をしてどのように問題を解決するか
(4)今後のキャリアプラン⇒事業実施後の収益計画
補助金を活用し事業を行うことで、今後5年間でどのような売上、利益が見込まれるかを説明します。いかがでしょうか。難しいイメージだった事業計画書も、少し理解しやすくなったのではないでしょうか。
これから補助金の申請を検討されている方は、このポイントを意識して作成してみてはいかがでしょうか。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
現在、弊社では事業再構築補助金第11回の申請についてご支援を進めさせていただいております。
今回はお客様がお持ちの「新事業に該当するのかがわからない」というお悩みについて少し掘り下げます。
注:本文内の再構築補助金に関する用語の定義は「事業再構築指針」より引用しています。
事業再構築とは
事業再構築とは、「新市場進出、事業転換、業種転換、事業再編、国内回帰のいずれかを行う計画に基づく中小企業等の事業活動」と定義されています。その中でも全く新しい事業をする、全く新しい製品を作るといった事業転換、業種転換に比べて、新しいことの説明が難しいのが「新市場進出(新分野展開)」です。
新分野展開とは
新分野展開とは、中小企業等が主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品を製造し又は新たな商品若しくはサービスを提供することにより、新たな市場に進出することをいう。
ここでいう「主たる業種又は主たる事業を変更することなく」とは、今の事業をそのまま続けることを意味します。
今までは航空機向けのバネを作っていたバネ製造業者が、設備を導入して初めて電気自動車のバネを作るようなイメージです。
但し、「商品若しくはサービス」「市場」に新規性がないと補助金の条件には該当しません。
航空機向けのバネと電気自動車向けのバネにはどのような違いがあるのか、コロナ禍においても電気自動車部品の需要は低迷しないのか等の説明を計画の中に盛り込む必要があります。事業者様からお話を聞く中でも、「何が新しい事業活動になるかが分からない」「設備を導入し便利にはなるけど、新しい事業活動には該当しないのではないか」というご心配も多いです。
しかし、詳しくお話させていただく中で、この話は補助金の要件に当てはまるのでは?といったお話を聞くことも多くあります。ご自身の考えられているお仕事が補助金の要件に該当するか不安な方は、お気軽にお問い合わせください。
-
こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
本日は事業再構築補助金の申請を検討されている方、採択されて手続きを進めておられる方にぜひ見ていただきたいお話です。事業再構築補助金の計画策定費用を減らす
事業再構築補助金の計画や申請資料を作成するのはなかなか骨の折れる作業です。そのため、計画の策定支援を専門家に依頼したいとお考えの方も多いと思います。
外部の専門家に依頼する場合、専門家に支払った費用のうち一部を補助してくれる制度を設けている自治体があります。
自治体によって制度概要は異なりますが、例えば東広島市では市税の滞納がないこと、市のモニタリングに協力すること、採択結果が発表されていること等の条件が、埼玉県では、第9回の申請を行う事業者の条件が設定されています。※本文中の説明は東広島市事業再構築促進サポート補助金および埼玉県事業再構築計画策定費用補助金を参考に記載しております。
自治体ごとに異なる要件が設定されておりますので、申請の際は各自治体の制度要綱を確認してください。事業再構築補助金の自己負担部分を減らす
事業再構築補助金は通常、税抜き投資金額の2/3を補助金として受け取れるものです。
しかし、自治体によっては自己負担部分の1/3についても一部補助を受けられる制度があります。
<補助金上乗せのイメージ>
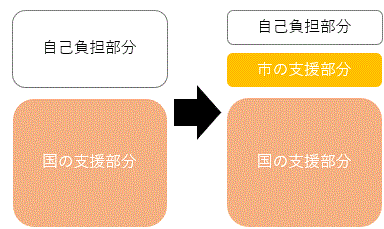
ただし、各自治体の定める期間において国の事業再構築補助金の交付の決定を受けている必要があります。
また上限金額や申込期間、必要となる書類も自治体によって様々です。※本文中の説明は和歌山市事業再構築支援補助金を参考に記載しております。
自治体ごとに異なる要件が設定されておりますので、申請の際は各自治体の制度要綱を確認してください。実施している自治体が限定的である、締め切りが近いといった制約はありますが、自己負担部分を少しでも減らすチャンスです。
気になる方は、一度「(所在地の自治体) 事業再構築」で検索してみてください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
今回のコラムは、事業再構築補助金の要件の1つである新規性要件、特に製品等の新規性要件についてです。
製品等の新規性と言われても、急に新しいことするなんて無理!と思われるかもしれません。そこで、改めてご説明させていただきます。
初めに、事業再構築指針で新規性要件は下記の3つとなっています。
・製品等の新規性要件
・市場の新規性要件
・製造方法等の新規性要件
今回は①の「製品等の新規性要件」です。これは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換(製造方法の変更)のほぼ全ての類型で必須要件となっています。
製品等の新規性要件については、
・過去に製造等した実績がないこと
・主要な設備を変更すること
・定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)
の3点を事業計画において示す必要がございます。
「過去に製造等した実績がないこと」
「過去に製造等した実績がない」の判断として、5年程度を一つの目安としていただければと思います。また、試作のみや、テストマーケティングのみの場合、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれると、公式から見解が出ております。
「主要な設備を変更すること」
既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。主要な設備(機械・装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します)を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることを示す必要がございます。
「定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)」
これは、性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることを示す必要がございます。例としては、既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等が、X%向上する等、数字で示すことができるかがポイントとなっています。
この3点を満たすことで、製品等の新規性要件を満たすこととなります。
今回は事業再構築補助金の要件である製品等の新規性要件について解説しました。
補助金活用をご検討の事業者様は、まず「急に新しいことするなんて無理!」と億劫にならず、上記内容を基にご検討いただければと思います。
「事業計画書の作成が難しい、分からない」、「どの認定支援機関が良いか困っている」という方はまず一度ご相談ください。
-
フラッグシップ経営代表、中小企業診断士の長尾です。
突然ですが、経営者の具体的な仕事とはいったい何でしょうか。
あまりに抽象的な質問ですが、私は具体的に10個くらい挙げることができます。
その中でも特に重要な3つを挙げろと言われれば私は下記の3つと答えます。
- 経営計画を立てること
- 顧客を創造すること
- 新商品(製品、サービス)を開発すること
中小企業の経営者がこの3つを疎かにしては持続的な発展は望めないと思います。
実は私が考える社長の仕事として重要な3つ具体的な仕事は、近年盛り上がりを見せている「ものづくり補助金」や「再構築補助金」に取り組むことで実践することが可能です。
補助金の申請は自社の強み・弱みの整理、市場分析など審査項目が多岐に渡っているため、現状と将来を検討した上で、具体的な市場やユーザーを想定し、損益計画も必要になります。
また、生産性の向上や革新性、新規性を要件としているため、新商品や製品、サービスの開発が求められています。
補助金の申請書を真剣に作成することで現状分析、新製品の開発、市場動向とターゲット顧客まで設計することができます。
その上、採択されれば返済不要の補助金を活用して設備投資を行うことができます。
先行きが不透明な時代だからこそ、経営者としての仕事をしっかりと取り組まなければなりませんが、経営者の仕事は抽象的で何から取り組むべきか分かりにくいと思います。
そこで補助金の申請書作成、採択後の設備投資を通して、経営計画を立てること、顧客を創造すること、新商品(製品、サービス)を開発することを実践してみてください。
事業の発展を必ずや後押ししてくれると思います。
-
こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
現在、数多くの補助金が存在しています。ものづくり補助金、事業再構築補助金etc…
例年実施されている補助金ですが、補助金取得における二次的要素を記載させて頂きます。
本来、事業計画・収支計画を毎年作成して月次等で管理を行うのが理想ですが、事業計画を作成されている事業者様は少ないのではないでしょうか。
申請書には自社の外部環境や強み、3~5年間の収支計画などを記載していただきます。
申請書を考える際に、自社の経営環境を改めて見直したり自社の強みを考えるきっかけになったりすると言えます。実際、お話を伺えば強みをお持ちの事業者様であっても、回答に詰まる方もいらっしゃいます。
また、申請書の作成を現代表だけではなく、次期経営者候補の方も一緒に行うことで自社の経営環境や強みの理解の促進に活用できます。
さらに、経営力向上計画などの各種中小企業支援政策を活用される場合には、補助金の申請書と同様に事業計画を記載して提出必要があります。
そのため、一度事業計画を作成しておくことで、各種支援政策申請における基礎資料とすることができます。
このように、補助金は二次的にも様々なメリットがあり、これらのメリットは採択可否によらず得られるものです。
このような二次的メリットも意識して補助金申請をご検討していただけますと幸いです。
-
こんにちは、株式会社フラッグシップ経営の㮈本です。
第4回事業再構築補助金の採択発表が、今月もしくは3月上旬には発表される予定です。
弊社でも40社近い事業者様のサポートをさせていただきましたので、毎日結果発表がないか気になっています。
事業再構築補助金も早いもので第1回目から1年が経過しようとしています。
発表当初は、どのような事業計画でも要件さえ満たしていれば採択されるなどインターネットなどで騒がれていましたが、実際の事業再構築補助金は現実的な計画が採択されている印象です。
弊社でも当初は、どのような事業計画書が採択されるのか前例がないため、手探りの状態でしたが4回の事業再構築補助金を経験して、事業再構築補助金の要件に合致した案件や要件に沿わない案件の簡単な判断ができるようになってきました。
その中で、事業再構築補助金の打ち合わせを行っているとご相談いただいた方から「この計画は通りますか?」といった意見や「採択されやすい事業を教えて欲しい」といった意見を聞くことがあります。
「採択されやすい事業を教えて欲しい」というのはそもそも私たちに自分が新しくする事業を聞くことがおかしな話であると思いますし、大抵こういった発言をされるケースは本業での経営にそこまで困っていない事業者の方が多いように感じます。
トレンドの補助金が欲しいから申し込みたい、自社のHPに事業再構築補助金に採択されたと掲載したいなどといった個人的な理由が多くを占めいています。
また、計画は考えたけど自分の趣味の延長やなんとなくお金があればやりたいといった事業者の方の多くは、「この計画は通りますか?」といった質問が多いように感じます。
このような質問をいただいた場合によく聞き返すのが、「自分の知り合いがこの内容の計画を建ててお金を貸してほしいと来た場合に、〇〇様はこの計画を見てお金を貸しますか?」と尋ねる場合があります。
今までこの質問をしたすべての方がNOと答えました。
自分でNOと思っている計画を補助金の事務局がYESといってくれることは極めて低い確率だと思います。
では、なぜNOなのかを話し合いながら計画書を作成するサポートをすると、計画として弱かった部分の理由などを考えることができます。
中には、この質問してそもそも計画の根本から考え直すといって一生懸命新しい計画を考え直す事業者の方もいらっしゃいます。
すべての計画書が通ることのない補助金なので、一生懸命考えても無事採択されるかはわかりませんが、自分がお金を貸す立場になった場合にお金を貸す相手に聞きたいことを計画書の中で見直すことも、事業計画書を書く上では重要となると思います。
