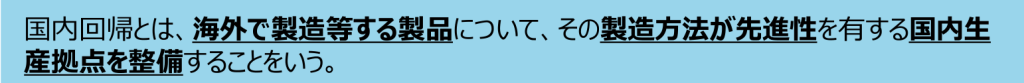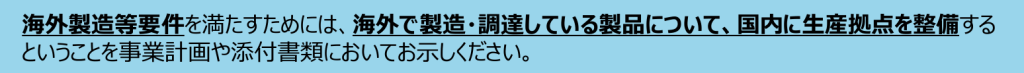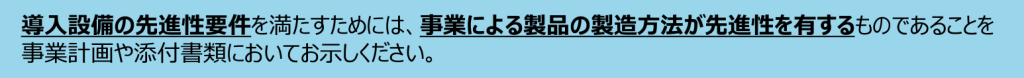公募要領
-
こんにちは、フラッグシップ経営の杉原です。
今日は、ものづくり補助金・事業再構築補助金ともに加点項目として認められる「えるぼし認定」「くるみん認定」についてご紹介します。えるぼし認定
この制度は、「女性活躍推進法」に基づいた制度で、一定基準を満たし、女性の活躍推進に関する状況などが優良な企業を認定するものです。〝女性が能力を発揮しやすい職場であるか〟という観点から、定められた5つの評価項目の合致状況によって認定の可否が決まります。また、合致度に応じて認定段階が決定します。
5つの評価項目
- 採用
- 継続就業
- 労働時間等の働き方
- 管理職比率
- 多様なキャリアコース
※5つの評価項目の詳細についてはこちらからご覧ください。
認定の段階
- 5つ全ての基準を満たす:3段階目
- 3~4つの基準を満たす:2段階目
- 1~2つの基準を満たす:1段階目
(さらに上の段階として「プラチナえるぼし認定」というのもあります)
項目ごとに基準達成状況の算出方法がありますが、「男女別の採用における競争倍率が同程度であること」や「女性労働者の平均勤続年数が、産業ごとの平均値以上であること」など、主に〝自社内での男女比率〟で判定するものと〝産業ごとの平均値以上かどうか〟で判定するもので構成されているようです。
えるぼし認定制度は認定されたら終わり、というわけではなく、5つの評価項目の実績を毎年「女性の活躍推進企業データベース」にて公表する必要があります。くるみん認定
くるみん認定は次世代育成支援対策推進法に基づいた制度です。行動計画を策定しその行動計画に定めた目標を達成するなど一定の要件を満たした上で、必要書類を添えて申請を行うと「子育てサポート企業」として厚生労働大臣の認定「くるみん認定」を受けることができます。
10項目の認定基準
- 雇用環境の整備について、行動計画策定指針に照らし適切な行動計画を策定したこと
- 行動計画の計画期間が、2年以上5年以下であること
- 策定した行動計画を実施し、計画に定めた目標を達成したこと
- 策定・変更した行動計画について、公表および労働者への周知を適切に行っていること
- 計画期間における、男性労働者の育児休業等取得率が10%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること。または、計画期間における男性労働者の育児休業等取得率および企業独自の育児を目的とした休暇制度利用率が、合わせて20%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること、かつ、育児休業等を取得した者が1人以上いること
- 計画期間における、女性労働者の育児休業等取得率が、75%以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイト「両立支援のひろば」で公表していること
- 3歳から小学校就学前の子どもを育てる労働者について、「育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置または始業時刻変更等の措置に準ずる制度」を講じていること
- フルタイムの労働者等の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満であること。かつ、月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者がいないこと
- 次の3ついずれかの措置について、成果に関する具体的な目標を定めて実施していること
- 所定外労働の削減のための措置
- 年次有給休暇の取得の促進のための措置
- 短時間正社員制度、在宅勤務、テレワークその他働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
- 法および法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと
※認定基準の詳細はこちらから
認定基準1~10をすべて満たしたらくるみん認定の申請を行えます。なお、基準を満たさなくなった場合は認定が取り消されますのでご注意ください。
ご紹介したどちらの制度も細かい要件が複数にわたって設定されているため、認定取得にチャレンジする場合は社会保険労務士などの外部専門家に相談するのがよいかと思われます。
今回ブログを書くにあたって初めて二つの制度の詳細について調べましたが、非常に手間がかかるものであり、補助金の加点を第一目的にして認定を受けるのは現実的ではないのではないか、という印象を受けました。「この制度の認定を受けていれば補助金申請の際に加点として認める」というものとしては、事業継続力強化計画やパートナーシップ構築宣言などの制度もあります。
これらの認定取得については当社でも多数の支援実績がございますので、お気軽にお問い合わせください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
しばらく再構築補助金の話題が続きましたが、今回は新たな公募要領が発表されたものづくり補助金について説明したいと思います。
ものづくり補助金は補助上限こそ少額ですが、再構築補助金と異なり何度でも申請が可能であり、既存事業の生産性向上(=たくさん作れる、よりよく作れる)に対する設備投資に補助が出るため、小規模な投資や定期的な投資にはぴったりです。15次公募の概要
趣旨
「中小企業自身の経営力を高め、事業計画期間にわたって生産性を高めることを支援する」
補助金の趣旨自体は前回の公募回から変更がありません。具体的にどれだけ改善できるのか?を計画書にしっかり記載しましょう。応募締切・採択発表
応募締切:令和5年7月28日(金) 17時
採択発表:令和5年9月下旬頃(予定)
締め切りは7月末と少し余裕があるように見えますが、油断するとすぐに締め切りがやってきます。
早めに設備投資内容を決定し、計画書の作成や資料準備に取り掛かりましょう。申請の要件
ものづくり補助金を申請するために必ず守らなければならない要件は下記の通りです。
①給与支給総額を年率平均1.5%以上増加させる
②事業場内最低賃金(補助事業を実施する事業場内で最も低い賃金)を毎年、地域別最低賃金+30円以上の水準とする
③事業者全体の付加価値額を年率平均3%以上増加させる①~③は、申請時に作成する事業計画の期間内(3年~5年)で達成する計画を策定します。
特に②に関しては、計画期間内に最低賃金の改定があった場合も含めて常に達成する必要があります。
賃上げを忘れていた、最低賃金を意識していなかった等の場合は補助金返還を求められます。ここまでは前回の公募回と同様の内容です。
追加された注意点
ここからは、第15回から特に注意すべき点として要綱に盛り込まれているポイントをご説明します。
従業員数の数え方について
ものづくり補助金において、従業員数は補助上限を決定する大切な指標です。代表取締役や監査役など、登記上の役員は従業員には含まれないことに注意が必要です。
要綱には「代表取締役や専従者等の常勤従業員に当てはまらない者が含まれていることが判明した場合、採択取消等になることがあります。」との記載が追加されており、設備やシステムの発注先について
同一代表者・役員が含まれている事業者、資本関係がある事業者を機械装置・システム構築費の発注先とすることはできません。
補助金採択後の手続きや報告について
補助金は採択された後にも、各ポイントで報告等の義務があります。
①交付申請
何をいくらで購入するのか、その設備・システムの内容について申請を行います。
この手続きが完了して初めて設備やシステムの発注ができます。
②実績報告
設備を導入した後、導入した証拠書類(写真や伝票関係、通帳の写しなど)を提出し、交付申請の内容通りに設備が導入されているかが確認されます。
③事業化報告
事業計画書通りに事業が行えているか、また賃上げ等表明した事項が順守されているかを報告します。
今回から要綱には、本手続きを怠った場合、または虚偽の報告を行った場合に「補助金の返還を求めることがあります。」との記載が追記されました。忘れずに手続きを行えるよう、事前に計画立てておきましょう。まとめ
要件や制度の趣旨に変更はありませんでしたが、注意点がいくつか追加されています。
特に誤りの多い点であるため要綱に盛り込まれていると思われます。
ご自身で計画書や申請資料を作成される際には、きちんと対応できているかを申請前に再確認してみてください。
どこに気をつければいいのか不安な方は、弊社がしっかりサポートいたします。
よろしければご相談ください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の杉原です。
事業再構築補助金10回公募の注意点シリーズ。3回目は公募要領に記載されている細かな注意点についてです。応募申請の際は、「申請要件はどんな内容か」「補助金がいくらもらえるのか」「どんなものを補助対象にできるのか」といったことが特に気になりますよね。ですが、それと同様に、公募要領中で何気なく読み流してしまっている文章が非常に重要なのです。
これらを把握しないまま応募申請し、採択された後に「採択取消」や「補助金返還」などの事態に発展することも…。
せっかく申請した事業計画や、採択が無駄にならないように、公募要領や補助事業の手引きは最初から最後までお目通しいただくことをおすすめします。今回のブログでは、トラブルになりがちなことや「え?そんなとこまで?」と思われがちな細かな注意点をご紹介いたします。10回公募から追記されたものと、以前から記載があったものの見落としが多い部分をピックアップしています。
ただし、あくまで抜粋したものですので、応募申請時や採択後手続き時はくれぐれも皆様ご自身で公式の資料をご参照ください。説明会への参加
- 応募申請前の説明会への参加
申請の前に、必ず事務局が実施する説明会に参加してください。説明会の詳細は、事務局HPを確認してください。(公募要領30ページ)
→2023年4月19日現在、事業再構築補助金事務局HPに案内はありません。今後更新されると思われますので随時HPを確認しましょう。- 採択後の説明会への参加
本事業に採択された事業者は、事務局が実施する説明会に参加しなければなりません。参加しない場合は、交付申請を受け付けません。(公募要領39ページ)
→過去公募回でも、採択された事業者様あてに事務局からメールにて採択後説明会の案内が届いています。10回公募から案内方法が変更になるかは不明ですが、どのような形であれ、「採択後の説明会には必ず参加しなければいけない」という点はお忘れなきようご注意ください。補助対象経費の内容による不採択・採択取消の可能性
計上されている経費の大半が補助対象外である場合、補助事業の円滑な実施が困難であるとして、不採択・採択取消になりますのでご注意ください。(公募要領35ページ)
→補助対象外となる経費については、同35ページに記載があります。当社でご支援する場合には、応募申請時点で補助対象外とみなされる可能性のあるものは除外するようアドバイスさせていただきます。保険または共済への加入義務
補助金額が 1,000 万円を超える案件では、本事業により建設した建物等の施設又は設備を対象として、次に定める付保割合を満たす保険又は共済(補助金の交付対象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を含む。)による損害を補償するもの)への加入義務を負うことについて同意していただきます。ただし、小規模企業者にあっては、この限りではなく、保険又は共済加入に代わる取組を実施することでも差し支えありません。
・小規模企業者 加入推奨(推奨付保割合 30%以上)
・中小企業等 30%以上
・中堅企業等 40%以上
(公募要領27ページ)
補助対象経費の支払方法
補助対象経費は、補助事業実施期間内に補助事業のために支払いを行ったことを確認できるものに限ります(外国通貨の場合は、支払日当日の公表仲値で円換算)。交付決定より前 (事前着手申請を得ている事業者は令和4年12月1日以前)に契約(発注)した経費は、いかなる事情があっても補助対象になりません。支払いは、銀行振込の実績で確認を行います(現金払・手形払等は対象外)。(公募要領36ページ)
→補助事業(設備等の投資)が終了した後に行う「実績報告」の際に、銀行振込を行った通帳のコピー等の提出が求められます。今回は公募要領に記載のあるポイントについてご紹介いたしましたが、以前コラムで取り上げた「収益納付」など補助事業の手引きの中にも注意が必要な箇所がございます。
補助金活用の際は、公募要領や手引きをよく読み応募申請するようお気をつけください。なお、記載してある文言がどういうことを意味しているのか?と理解しづらいものもあるかと思いますが、その際は当社にお気軽にお問い合わせください。
-
こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
前回に引き続き、第10回公募の詳細をご説明いたします。
枠がかなり多く混乱されている方もいらっしゃると思いますが、今回は申請にあたってどんな要件があるのか?についてです。各枠の要件について
第10回は全部で8つの申請枠がありますが、申請を検討しやすいのは下記の4枠です。
 中でも第9回までの要件とほぼ同様である物価高騰対策・回復再生応援枠が最も申請しやすい枠であると言えます。
中でも第9回までの要件とほぼ同様である物価高騰対策・回復再生応援枠が最も申請しやすい枠であると言えます。事業再構築要件
すべての枠に共通する要件です。 従来からあった要件で、「新事業を行うこと」が要件となります。
何が新事業とみなされるのか、の定義ですが下記の4点がポイントです。
・主要な設備を変更する・新たに行う事業が売上全体の10%を占める損益計画を立てる
1000万円の売上があれば、そのうち100万円以上は新事業による売上でなければなりません。・過去に製造等した実績がない
社内で既に製造・販売した経験がある場合は対象になりません。
市場にある製品等であっても、当社にとって初めて製造する製品であれば対象です。・既存事業との代替性がないこと
既存の製品又は既存の商品若しくはサービスの需要が、新製品又は新商品若しくは新サービスの需要で代替される場合は対象になりません。認定支援機関要件
すべての枠に共通する要件です。
事業計画について認定経営革新等支援機関の確認を受けていることが必要です。 また、受け取る補助金の金額が3,000万円を超える場合、金融機関の確認も追加で必要です。付加価値額要件
すべての枠に共通する要件です。
事業計画の中で、付加価値額の年率平均3.0%以上増加させることを示す必要があります。
付加価値額とは営業利益、減価償却費、人件費を足し合わせたものを言い、3年の計画であれば9%、5年の計画であれば15%増加させる計画を策定しなければなりません。
成長枠に関しては成長分野へ展開することが要件であるため(後述の市場拡大要件)、年率平均4.0%以上増加することと少し条件が厳しく設定されています。市場拡大要件
成長枠で申請する場合の要件です。
事業再構築の中で取り組む事業が、過去~今後のいずれか10年間で、市場規模が10%以上拡大する業種・業態に属していることが必要です。
再構築事務局から当該市場が指定されていない場合は、ご自身で市場を調査し、統計的に増加していることを示さなければなりません。給与総額増加要件
成長枠で申請する場合の要件です。
事業計画の中で、給与支給総額を年率平均2%以上増加させることを示す必要があります。
ものづくり補助金の賃上げが1.5%が必須条件であることに対し、再構築の成長枠では2%が条件です。最低賃金要件
最低賃金枠で申請する場合の要件です。
①2021年10月から2022年8月までの間で
②3か月以上最低賃金+30円以内で雇用している従業員が
③全従業員数の10%以上いること
が必要です。売上高減少要件
最低賃金枠・物価高騰対策回復再生応援枠で申請する場合の要件です。
過去の公募回と考え方は同様ですが、取れる期間に変更があります。
①2019年から2021年までの3年間の売上、②2022年以降の売上とした場合、①と②を比較して10%以上減少していることが条件です。
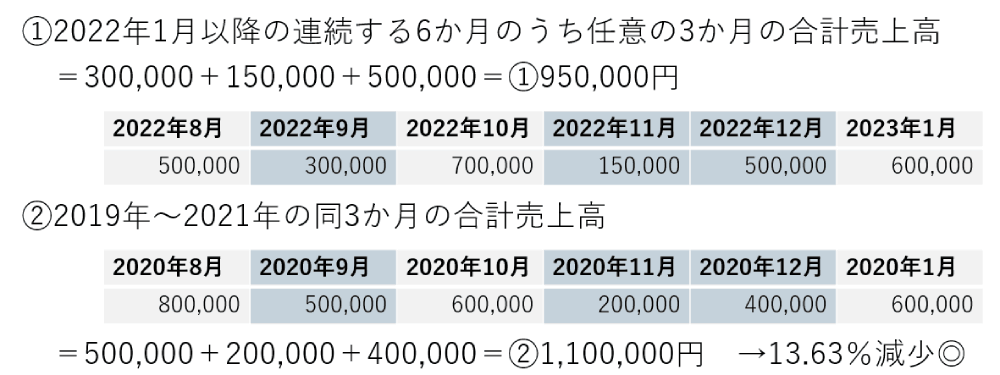
市場縮小要件
産業構造転換枠で申請する場合の要件です。
現在の主たる事業が過去~今後のいずれか 10 年間で市場規模が 10%以上縮小する業種・業態に属しており、当該業種・業態から別の業種・業態に転換する必要があります。
市場拡大要件と同様に、再構築事務局から当該市場が指定されていない場合は、ご自身で市場を調査し、統計的に増加していることを示さなければなりません。上記のような要件があり、弊社では最も申請しやすい物価高騰対策・回復再生応援枠での申請をおすすめしております。
みなさんはどの枠が気になりましたでしょうか。興味を持たれた方はぜひご相談ください。 -
こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
今回は、皆さまも気になっている事業再構築補助金第10回から新設されたサプライチェーン強靭化枠について解説させていただきます。
サプライチェーン強靭化枠とは?
⚫海外で製造する部品等の国内回帰を進め、国内サプライチェーンの強靱化及び地域産業の活性化に取り組む事業者(製造業)を対象として「サプライチェーン強靱化枠」を新設し、補助上限額を最大5億円まで引き上げて支援。
補助率:中小企業者等1/2以内、中堅企業等1/3以内
といった枠になります、ポイントは国内回帰ですね。
今回は特に国内回帰についてご説明させていただきます。
国内回帰の定義(案)
国内回帰の該当要件(案)
本事業の対象となる国内回帰とは、次のいずれにも該当する場合をいう。
(1)事業を行う中小企業等が海外で製造・調達している製品について、国内で生産拠点を整備すること※【海外製造等要件】※ただし、事業を行う中小企業等が取引先から要請を受けて、取引先が海外から調達している製品を製造する生産拠点を国内で整備する場合も特例的に対象とみなします。
(2)事業による製品の製造方法が先進性を有するものであること【導入設備の先進性要件】
(3)次に掲げる要件のいずれかを満たすこと
(ⅰ)事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、総売上高の十分の一又は総付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。
(ⅱ)令和3年11月以前の直近の事業年度の決算に基づく売上高が10億円以上であり、かつ、同事業年度の決算に基づく売上高のうち、事業再構築を行う事業部門の売上高が3億円以上である場合には、事業計画期間終了後、本事業により製造する製品の売上高又は付加価値額が、当該事業部門の売上高の十分の一又は付加価値額の百分の十五以上を占めることが見込まれるものであること。
上記3点が国内回帰のポイントとなります。
詳細は下記させていただきます。
海外製造等要件(案)
①海外で製造・調達している製品であること
事業により製造する製品について、事業を行う中小企業等(申請者)が海外で製造・調達している製品であることを、以下のa及びbによりお示しいただく必要があります。
a:当該製品について、2020年1月以降に海外から調達した実績があること(例:2020年~2022年の各年における海外から国内への当該製品の納品量等)
b:2020年1月以降の当該製品の海外への発注及び海外からの納品の事実(a.を裏付ける取引の実績)(例:上記を満たす、1つの取引に関する発注書及び納品書等)
※申請者が取引先から要請を受けて、取引先が海外から調達している製品を製造する生産拠点を国内で整備する場合は、上記a及びbは取引先についてのものであること。
②国内に生産拠点を整備する計画であること
導入設備の先進性要件
①先進的な設備を導入すること
既存設備と同程度の設備で製造することは、製造方法が先進性を有するとはいえません。補助事業により導入する全ての設備が特注品又は製造機器メーカーの最新カタログに掲載されているものであることをお示し下さい。
②導入設備の導入効果を証明すること
性能や効能を定量的に説明することで、生産性や付加価値向上等の導入効果があることをお示し下さい。
(例:○○部品の製造にあたり、○○設備を導入することで、○○加工を行えるほか、生産効率がX%向上する等)
上記が国内回帰の要件となります。
やはり、「サプライチェーン強靭化」というだけあり、顧客を巻き込んで要件を満たすこともある内容となっております。
現段階で公表されている内容は「案」ですので、公募要領が発表される際には見直される可能性もございます。
しかし、補助上限額が5億円と高額なことから、採択率は低くなることや、一度の公募回で予算消化の可能性もございます。
このような枠での申請には、採択ポイントを押さえた事業計画を策定する必要があるため、対象となりそうな事業者様は今からでも準備をしておくことをおすすめします。
-
こんにちは、フラッグシップ経営の橋本です。
先日、江口から簡単に第9回公募(3月24日締切)と第10回公募(令和5年3月下旬より公募開始予定)の違いをご説明させていただきました。
要領も出ておらず、未確定要素の多い新予算ですが売上要件の緩和により申請可能な事業者様の幅が広がり得る一方で、現在申請可能な事業者様の申請が不可能になる可能性も高いと考えています。
本稿では、新予算における申請枠の紹介と補助対象事業者を簡単にご紹介させていただきます。
第9回公募(現在募集中)では下記のいずれかに該当する事業者が補助対象となります。
補助要件①:2020年4月以降の売上が減少している。
補助要件②:グリーン成長戦略への展開
第10回公募では下記のいずれかに該当する事業者が補助対象となります。
補助要件①:2022年1月以降の売上が減少している。
補助要件②:公募開始時に指定される市場規模が10%以上拡大する成長分野への展開を行う。
補助要件③:グリーン成長戦略への展開を行う。
補助要件④:公募開始時に指定される市場規模が10%以上縮小する重点支援業種に属する。
補助要件⑤:生産拠点を国内回帰する事業を行う。
以上の通り、第10回公募では申請枠によっては売上要件の撤廃等、補助対象となる事業者の幅が広がる一方で、求められる取組内容に規制が加わり、第9回公募では申請出来たが第10回公募では申請が不可能になる事業者様も一定数発生するのではないかと考えています。
公募要領が発表されましたら詳しくご案内させていただきますが、事業再構築補助金の申請をご検討されている事業者様、特にご自身で申請を行った結果、不採択となってしまった事業者様はお早めにご相談ください。
-
こんにちは、フラッグシップ経営の秋定です。
今回のコラムは、事業再構築補助金の要件の1つである新規性要件、特に製品等の新規性要件についてです。
製品等の新規性と言われても、急に新しいことするなんて無理!と思われるかもしれません。そこで、改めてご説明させていただきます。
初めに、事業再構築指針で新規性要件は下記の3つとなっています。
・製品等の新規性要件
・市場の新規性要件
・製造方法等の新規性要件
今回は①の「製品等の新規性要件」です。これは、新分野展開、事業転換、業種転換、業態転換(製造方法の変更)のほぼ全ての類型で必須要件となっています。
製品等の新規性要件については、
・過去に製造等した実績がないこと
・主要な設備を変更すること
・定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)
の3点を事業計画において示す必要がございます。
「過去に製造等した実績がないこと」
「過去に製造等した実績がない」の判断として、5年程度を一つの目安としていただければと思います。また、試作のみや、テストマーケティングのみの場合、従来販売していた製品の改善を通じて事業再構築を図る場合は「過去に製造等した実績がない場合」に含まれると、公式から見解が出ております。
「主要な設備を変更すること」
既存の設備でも製造等可能な製品等を製造等することは、事業再構築によって、新たな製品等を製造等しているとはいえません。主要な設備(機械・装置、プログラム(データを含む。)、施設等を指します)を変更することが新たな製品等を製造等するのに必要であることを示す必要がございます。
「定量的に性能又は効能が異なること(計測できる場合)」
これは、性能や効能の違いを定量的に説明することで、新たな製品等であることを示す必要がございます。例としては、既存製品と比べ、新製品の強度、耐久性、軽さ、加工性、精度、速度、容量等が、X%向上する等、数字で示すことができるかがポイントとなっています。
この3点を満たすことで、製品等の新規性要件を満たすこととなります。
今回は事業再構築補助金の要件である製品等の新規性要件について解説しました。
補助金活用をご検討の事業者様は、まず「急に新しいことするなんて無理!」と億劫にならず、上記内容を基にご検討いただければと思います。
「事業計画書の作成が難しい、分からない」、「どの認定支援機関が良いか困っている」という方はまず一度ご相談ください。
-
こんにちは、フラッグシップ経営の江口です。
先日のものづくり補助金に続いて、事業再構築補助金の要綱も発表されました。
第8回公募と大きく変更がある箇所はありませんでしたが、次の第9回からは変更が予定されています。9回、10回公募のちがい 9回公募 10回公募 対象となる人 コロナ禍で売上・利益に影響を受けた企業・事業者 コロナ禍などの外的環境変化や自社の市場縮小に影響を受ける企業・事業者など 補助上限金額 2,000万円~8,000万円
(通常枠)2,000万円~7,000万円
(成長枠)補助割合 投資額の2/3 投資額の1/2 対象となる設備 2021年12月20日以降に発注した設備 2022年12月2日以降に発注した設備 補助率の引上げ 〇
(売上が直近で一定割合減少している場合)〇
(賃上げを実施する場合)申請締め切り 令和5年3月24日 不明
(令和5年3月下旬より公募開始予定)9回公募は前回(第8回)と同様の要件で、補助額・補助割合ともに据え置きです。引き続き売上減少の要件があり、補助割合の引き上げも「コロナ前と直近を比較して売上等が減少している」ことが必要でした。
10回公募は売上が減少していなくても申請できる枠が増加しており、これまで条件に合わなかった方でも申請ができるようになっています。コロナ禍の影響を受けただけではなく、政策的に推し進めていく分野や賃上げ・成長分野への投資など、国内の競争力を強化する取り組みについても重点的に支援がなされている印象です。一方、補助額や補助割合の引き下げ、事前着手期間の短縮など、規模感の比較的小さい投資やこれからの投資に向いている印象です。第8回と第9回の変更点を比較して、自社の取り組みにはどちらが合っているのか、検討してみてください。弊社でもご相談を受け付けております。